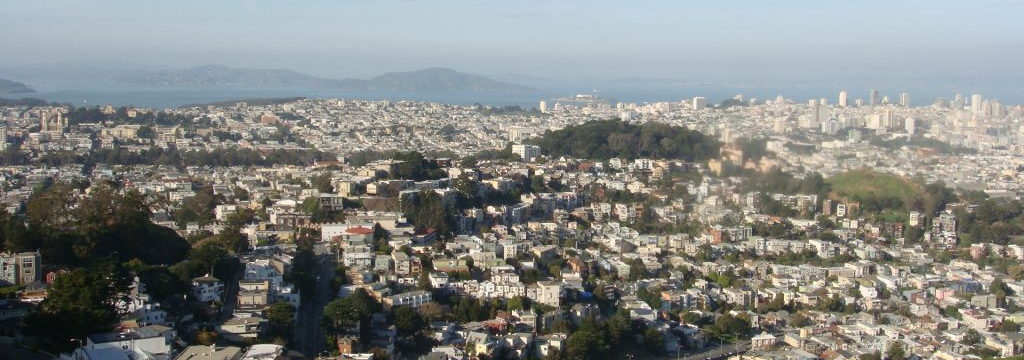
雑談・放談
かつて日本は、製造大国と呼ばれていました。
しかしここ30年、元気がありません。
どうしたんでしょうか。
どこに問題があるのか、あれや、これやと思い巡らしてみたいと思います。

現場改善会計論;無能と詐欺が織りなすScience Fictions の1例
現場改善会計論(以下、GKC)の第一の目標は「「改善効果の金額評価による見える化」でした。「設計情報転写論」や…
現場改善会計論 捏造の背後にあるものは? 過失か、詐欺か、、
東大教授の支援があり、京大教授との共同研究である現場改善会計論(以下、GKC)。10年余りの歳月をかけ、科研費…
現場改善会計論;研究手法も含めて、関係論文はすべて“NULL”である
現場改善会計論(Gemba Kaizen Costing, 以下GKC)をさまざまな斬り口でみてきました。どこ…
現場改善会計論;「改善効果の見える化」・・・100年前のはなしですか?
「時間」をキーワードに現場改善会計論(以下、GKC)を斬ってみました。論文の中にも時間が論理構成上重要な要素で…
現場改善会計論;砂上の楼閣か、蜃気楼か、
現場改善会計論(以下、GKC)の論理構成のキーワードは「時間」ではないかと考え、 「製造現場における改善効果測…
現場改善会計論;時間概念もデタラメ
現場改善会計論(以下、GKC)の“オソマツさ”は、半端じゃありません。なぜ、こんな論文が学会から賞を授与された…
現場改善会計論; “オソマツ” の一語に尽きる
現場改善会計論(以下、GKC)は、「机上の空論」。論理は支離滅裂。実現性も実用的効用もまったくなし・・・と、こ…
「現場改善会計論」は机上の空論か
個別原価計算表で、部分的な改善効果を反映させたりすると、計算結果がガラガラ変わる。これじゃ、個別の原価を計算す…
個別原価計算;固定費の配賦を止めたらどうなる?
会計はシロウトですが、前回は個別原価計算の “?な” ところを指摘させていただきました。 原価低減とかコストダ…
個別原価計算の罠に落ちた「現場改善会計論」の幼稚さ
矢橋林業(株)の現場改善を指導したのはOJTソリューションズ(以下、OJTS)。 「トヨタ式の本質はどのような…
OJTソリューションズ;羊頭狗肉になっていませんか?
OJTソリューションズ(以下、OJTS)は、矢橋林業(株)で行われた「現場力の向上Project(以下、現場力…
OJTソリューションズ;TPSの弱点を自覚しているか
前回は、現場改善会計論が依拠している「設計情報転写論」(藤本隆宏元東大教授)とトヨタ生産方式(TPS)、および…